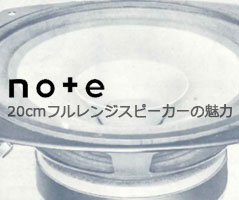トピックス
《後編》 道具は「生き様」 〜ヴァイオリンの音作りと「ものづくり」〜
FOSTEXスペシャル・インタビュー 﨑谷直人(ヴァイオリン)
インタビュー:2025年4月22日(火)、フォスター電機株式会社本社(東京都昭島市)

インタビューの途中で、新発売となるスーパーツィーターシステムGS17Hを、ご自宅で愛用中のGS103A-VBと組み合わせた音を聴いてみたら、オーディオ熱に火がついてしまったかも知れない(?!)ヴァイオリニストの﨑谷直人さん。インタビューの前編では2025年から始まった「アーティスト・レクチャー・シリーズ」を中心に、プライベートでお聴きになる音楽等についてお話を伺いました。後編では、音を聴く道具としてのスピーカーだけでなく、アーティストが音を作り上げていくために最も大事な道具であるヴァイオリンと弓、さらには音楽以外の趣味に関する道具まで、﨑谷さんが生活の中で「もの」とどのように接しているか、様々な道具から、さらには「ものづくり」へと話題が広がっていきます。
(前編から続く)
Q. スピーカーは音を聴く道具ですが、やはり﨑谷さんにとっては一番大事な道具といえば、もちろん楽器だと思います。
(﨑谷)
楽器は、難しいですよね。楽器だけで何時間でも喋りたくなってしまいますが、今日は楽器について日頃思っていることを1つだけ。
私のロジェーリは1697年に作られていて、この世に生まれてから300年以上が経過しています。ヴァイオリンは骨董品の側面があるので、お金があればいくらでも良い楽器を買えるかもしれません。でも、楽器を手にするということは、ただお金を払って手にいれる、ということではないと思っています。素晴らしい楽器は世に生まれてから、何百年と、人間の寿命より長く生きていくものですから、自分が手放した後も、次の人に引き継がれていきます。楽器を手にするということは、自分が弾く数年から数十年「お預かりする」という責任を伴うことだと思っています。これまでの持ち主にも敬意が必要です。
楽器を所有するためには、弾きこなす技術が必要なのはもちろんですが、メンテナンス等、保存していく技術も必要になります。楽器を乱雑に扱うような人を見てしまうと、個人的には残念に感じてしまうこともあります。でも、巨匠と呼ばれる演奏家の中には、楽器もクリーニングせずいつも松脂だらけで、楽器の扱い方は無頓着なのですが、楽器から出ていく音楽だけを追い求めて演奏するような方もいます。そういった演奏家は、楽器だけでなくて日常生活から全て、万事がそうなのです。ステージに上がるときの服装とかも全く拘らない。自分の生活とかどうでもよく、ただ音楽を優先しているような生き方です。そこまでいくと、もうその存在自体がアートのようで、その生き様がそのまま音になっているように思えて、カッコいいと思います。道具をどのように扱うか、それは生き様だと思います。
他の名器と同じように、私のロジェーリもいつかは次の人が手にするわけですから、自分も大事にしたいと思いますし、次の人にも大事に使って欲しいと私自身は思っています。

Q. きっと﨑谷さんは楽器への接し方と同じように、身の回りの道具も大事にされるのだろうなと思います。今回はFOSTEXスピーカーとのご縁があったわけですが、このような、楽器以外の道具を手にするときは、どのような視点で選びますか?
(﨑谷)
オーディオは、楽器や車のようにお金がかかる印象があって、敬遠していたところがあるので分かりませんが、私がこれまでにお金を使ってしまったなと思っているものに、腕時計があります。腕時計はとても好きで、一時期は十本近く持っていたりして、コレクションしていました。ちょうど最近、そのほとんどを手放して、今は数本を残すだけになりました。時計も上を見れば何千万円のものまで、楽器のように様々です。個人的にカッコいいと思う時計には百万円を超えるものも少なくありません。でも今は、時計単体としてカッコいいと思うものと、自分が身につけて自分らしく感じるかというのは別の問題だなと思うようになりました。以前は本当に惚れ込んで数百万円するスイス製の時計を持っていたりしたものですが、今日身につけているものは数万円で手にすることができる国産の時計です。これは、私が子供の頃憧れていた、仮面ライダーと関連があるデザインなので気に入っています。藤岡弘さんが演じる初代仮面ライダーこと本郷猛が劇中で使用していた、1960年代の腕時計のデザインをもとに、最近復刻された限定モデルです。この時計は気軽に持ち出せますし、仮面ライダーへの思い入れもあるので、自分らしくいられるような気がします。以前は、時計そのものがカッコいいかどうかに注目していましたが、最近は、道具として実生活で違和感なく使用できるかどうかを大事にするようになってきたように思います。モノ単独のカッコよさに簡単に心惹かれてしまうことから卒業したイメージです。
趣味の道具は、時計だけでなくオーディオも同じで、本当に好きな人は、何百万円、何千万円、それこそ破産するのではないかという勢いで、お金を注ぎ込む人もいると思うのです(笑)。オーディオもそういう「沼」みたいな分野だと思っていたから、近付かないようにしようと敬遠していたのかも知れませんが、今、自宅で楽しんでいるFOSTEXのスピーカーは、私の生活環境にちょうどよく溶け込んでいると思います。これが百万円以上と言われたら、手にするのを躊躇してしまうと思うのですが、十万円強というリーズナブルな価格で、これだけ音を楽しめるのは、道具として実直に感じられますし、多くの人におすすめしたいですね。


Q. 日常生活の道具と違い、先ほどお伺いしたように楽器は徹底的に拘っておられると思いますが、レクチャーでは弓の違いによる弾き比べも印象的でした。
(﨑谷)
レコーディングや演奏会でどのような音が欲しいかによって、ヴァイオリンも弓も使い分けをします。ヴァイオリンは、最近新しい楽器との出会いもありましたが、ロジェーリを使い続けるのは変わらないと思います。その一方で弓は、新しいものを手にしたり、手放したり、出たり入ったり、が多いかも知れません。演奏して自然に感じられる弓は、その時々で違いますね。それは、その時に取り組んでいる仕事の性質によるのかもしれません。
それでも、どうしても手放せない弓があります。それは子供のときから弾き続けてきた弓です。資産的な価値はほとんどないと思いますし、私以外の演奏家にとっては全く魅力がない弓かも知れません。でも、私にとっては本当に良い音が出る弓で、形もぐにゃぐにゃで真っ直ぐでないのですが、手放そうと思ったことはありません。名もなき弓ですが、一番弾いている時間が長くて、もはや身体の一部のようになっているのかも知れません。

Q. 道具が身体、指先に溶け込んでいるということですね。指先で扱う道具といえば、﨑谷さん、趣味でヨーヨーをされています。リハーサルのときに、ヨーヨーの腕前を披露していただいたのは、大変驚きました。
(﨑谷)
ヨーヨーは、今日も持ってきています。持ち歩きができるという点では身近な道具の1つかもしれません。これです(笑)。
(ヨーヨーを鞄から取り出し、ヨーヨー技を実演し始めながら)
楽器と同じ点は、ブレが生じてはいけないことです。思い返すと、子供の頃はけっこう上手な方だったと思います。子供の頃は、もうこれ以上ヴァイオリンを練習したくない、そう思うことが多々あったのですが、そういうときにヨーヨーを取り出していたと思います。でも、ヨーヨーの練習は、楽器と同じ要素があったからこそ、上達したのだと思います。ヴァイオリンの練習では、上手く弾けない箇所を分解して練習します。ヨーヨーでもそれと同じような練習をしていました。この動作ができたら、次にどう動かすか、その前後の動作をどのようにつなげるか、という風にヨーヨーを練習していました。これは、楽器で弾くのが難しいパッセージや小節、それぞれを弾けるようにして、その前後をどのようにつなげるか、何度も繰り返し練習するのと同じです。ヨーヨーをこう動かす動作が完了し、その後動きを止めたら、ここで糸の上に乗せる、という風に分解することができます。

Q. お見事!今のを動画に撮って何度も繰り返し見ながら練習しても、私にはできるようになる気がしません(笑)。
(﨑谷)
子供の頃、当時はYouTubeのような動画もないので、少年漫画の雑誌を見て、そこに描かれたイラストや、手順を指示するわずかな言葉をもとに練習していました。頭を使わないと遊ぶことができなかったのです。例えば、簡単なイラストとともに「奥の方に、一回し」と一言でしか説明が書かれていないのです。ここに書かれた「一回し」ってどういうこと?!ってなります。少ない情報しかないので、想像力を働かせないと、何をすれば良いのか分かりません。今はインターネットで動画を見ればゴールは分かりますが、当時は、そのゴールを探すところから考えるのが「遊び」たったのだと思います。得られる情報量が少ない時代だったからこそ、受動的にコンテンツを消費するのではなく、自身が能動的に頭を使わないと娯楽が得られなかったのです。ヨーヨーのような玩具は、技を身につける必要がある玩具ですから、スキルトイ、と呼ばれるそうです。その意味では、ヨーヨーは楽器と近いものかも知れません。
Q. ユーザー自身が能動的に働きかける必要がある道具であることは、ヨーヨーも楽器と同じですね。先ほどのお話で興味深く感じたのは、ヴァイオリンの練習は細部の積み重ねである、ということでした。音楽の世界では、私のようなアマチュアが演奏の指導を受ける場面でも、細部ばかりに注目していると、音楽の全体を見失ってしまう、と言われることがあります。
(﨑谷)
昨年、初めてイタリアに行く機会がありました。そのときに美術館でレオナルド・ダ・ヴィンチの点描の絵画を見ました。私は絵画のことはよく分からないのですが、それでも圧倒されるような素晴らしさを感じました。もしかすると、音楽や演奏を作り上げていくことは、点描の絵画を描くようなものなのかも知れません。その絵画は遠くから見ると圧倒されましたが、間近で点描の筆致一つ一つを見ていても、何を描こうとしているのかはまるで分かりません。でも、この細部が確実に描き切れているからこそ、絵画全体の圧倒的な説得力が生まれるのではないかと思っています。これは音楽も同じだと考えています。細かい部分の練習だけをしていては、全体感が損なわれるというようなことが言われることもありますが、私はそう考えません。細かい部分を、納得できるまでに弾けるようにした上で、さらに全体をまとめた表現を作ることが、私たちアーティストの仕事だと思っています。細部と全体、どちらが優先されるかということはなく、どちらも納得できるまで取り組むべきなのです。もちろん、アマチュアの演奏家であれば、限られた時間の中で何ができるか考えることは必要ですが、音楽の全体を形作るために、細部は軽視しても良い、ということにはならないと思います。

Q. 楽器に取り組むのと同じ姿勢で、ヨーヨーとも向き合っていらっしゃるんですね。それにしても、ヨーヨー、1つだけでなく、たくさんお持ちですね!
(﨑谷)
腕時計を集めていたときと同じ感覚かも知れません。ヨーヨーは、回転するベアリングの滑らかさや、ボディを金属の塊からの削り出しして作っているとか、色々「ものづくり」として見どころがあります。そういう「良いもの」に惹かれてしまい、ついつい増えてきちゃいました。腕時計も中身の機械や、ケースの加工技術、等と色々拘ってしまうのと同じです。
FOSTEXのスピーカーも、良い音を追求するために人の耳で、様々な試行錯誤があると先ほど伺いました。そのような人の手による「ものづくり」に興味を惹かれるのは、父親が、町工場を経営していて、子供の頃から「ものづくり」が身近な環境で育ったからだと思います。父は自動車部品の金型を作ったりしています。先ほども、スピーカーの音は、数値だけで決めることができないから人間が決める、と伺いましたが、私の父の仕事も、ただデータがあれば形が出来上がるわけではないということは何となく分かっています。
さらに父の先代、創業した祖父はとても器用な人で、当時祖父が作ったという竹細工を見たことがあるのですが、とにかく精緻で感動したことを鮮明に覚えています。私自身、手先が器用だとは思いませんが、音を作り上げていく姿勢は、実は、代々の「ものづくり」の血筋によるものかなと思うことがあります。
やはり父も器用で、自分で何でも作ってしまう人でした。今回のレクチャー・シリーズでFOSTEXのスピーカーを使うことを父に話したら、私が生まれるよりずっと前の若い頃にFOSTEXのユニットを購入して、箱を自分で作り、スピーカーを楽しんでいたという話を聞いて驚きました。親子二代でFOSTEXの音にお世話になったという不思議なご縁で、ますますFOSTEXを身近に感じました。
Q. 﨑谷さんの音色は、「ものづくり」のDNAがベースにあるのかも知れません。
今回、レクチャー・シリーズの会場でCDの音を聴いたスピーカー(GS103A-VB)で、私はFOSTEXに出会ったわけですが、測定できる数字だけでは限界があって、最後は人の耳で音を選んで決定していく「ものづくり」のプロセスは、ヴァイオリンの音作りと同じだと思いました。AIで音楽を作ることができてしまう時代ですが、人間であるアーティストは、AIでは作ることができない音楽を生み出していかないといけないと思いますし、それができなければアーティストの存在意義はなくなってしまうと思います。
スピーカーも、最終的には人が音を耳で聴いて選んで作っているから、素晴らしい音になるのだと思います。それと同じように私も、ヴァイオリンでお客さんに聴いていただきたい音を自分自身で選んで、新しい音を作り上げていきたいと思います。これから新しい表現の引き出しを増やしていくためにも過去の録音を改めて聴いていきたいと思います。今回のレクチャー・シリーズをきっかけに出会えた、このスピーカーで、たくさん音楽を楽しみながら聴いていきたいと思います。
それと、私自身が代表を務め、プロデュースを行うレーベルの仕事を、これからは増やしていきたいので、レコーディングで使うヘッドホンにも拘ってみたいです。FOSTEXはこのスピーカーだけでなく、以前にヘッドホンも聴いたことがありますが、その音も素晴らしかった印象があります。この後、ここに並んでいるヘッドホン、聴いてみたいです!
(FOSTEX)
色々なヘッドホンご用意しましたので、お帰りになる前に聴いていってください!

Q. ヘッドホンも﨑谷さんが気に入る音があるかも知れません。今日は、音楽以外の興味深いお話も含めて、貴重なお話をどうもありがとうございました。最後に一言お願いします。
(﨑谷)
初めて取り組んだ3回のレクチャー・シリーズで、「このように音が聴こえてほしい」と私が思い描くヴァイオリンらしい音を再生してくれるFOSTEXと出会えたことは、ヴァイオリン弾きとして本当に良かったと思っています。今後もレクチャー・シリーズを続けていきますので、引き続きFOSTEXの音と一緒に、録音芸術について様々なテーマで語っていきたいと思います。
最後に、GS103A-VB、本当におすすめです(笑)。このインタビューを読んだ皆さんも是非一度は音を聴いてみて欲しいです!

伝統工芸の漆塗りを施したTH900mk2をはじめとするヘッドホンのフラッグシップモデルを試聴

【YouTube動画紹介】
○「﨑谷直人アーティスト・レクチャー・シリーズ」各回の動画
第2回 ベートーヴェン/歴史的録音の深みをコンサートマスターの視点を交えて語る
第3回 バッハ/レコード創作にかけるアーティストの情熱 ~録音・ミキシング実演~
【﨑谷直人プロフィール】
○﨑谷 直人
1998年ノボシビルスク国際コンクールジュニア部門第1位、メニューイン国際コンクールジュニア部門第3位を獲得し、ケルン音楽大学に最年少 15歳で入学。その後パリ市立音楽院、桐朋学園ソリスト・ディプロマコースを経て、バーゼル音楽院修了。2006年にウェールズ弦楽四重奏団を結成。第1ヴァイオリン奏者として、ミュンヘン国際コンクール弦楽四重奏部門、大阪国際室内楽コンクール弦楽四重奏部門にて各3位を獲得。メナヘム・プレスラー、アレクサンダー・ロマノフスキー、ポール・メイエ、ミッシャ・マイスキー各氏ほか、多くのトップアーティストらと室内楽を共演。2014年より8年間、神奈川フィルハーモニー管弦楽団 ソロ・コンサートマスターを務めた。これまでに、東京フィル、京響、神奈川フィル、名フィル、バーゼル交響楽団、ノボシビルスク・フィル等とソリストとして共演。また、全国のオーケストラに客演コンマスとして出演。自身が代表を務め、プロデュースを行うkKy recordsを2023年に設立し、録音にも精力的に取り組む。
※演奏会やCDリリース等の詳細は公式サイト( https://www.naotosakiya.net/ )をご覧ください。
【インタビュアー紹介】
○取材・文・写真: 加藤 太一(公益財団法人日本科学技術振興財団・科学技術館)
科学技術をテーマとする国や企業等によるイベント等の企画・運営業務に従事。財団入団前2017年まで在職していたフォスター電機株式会社においてスピーカー関連業務に携わった経験を活かし、音について学ぶFOSTEXスピーカー工作教室の科学技術館や学校等における開催に2020年から協力。「﨑谷直人 アーティスト・レクチャー・シリーズ」では、﨑谷氏が対談する専門家や、会場でのオーディオ鑑賞環境のコーディネートを主に担当。音に関するハードの技術面に、ソフトとしての音楽が持つ魅力を組み合わせ、子どもの探究心のみならず大人の知的好奇心も満たしていくような取り組みに関心を持ち、録音芸術やその技術をテーマとする「アーティスト・レクチャー・シリーズ」に協力した。